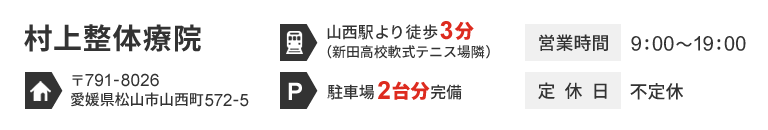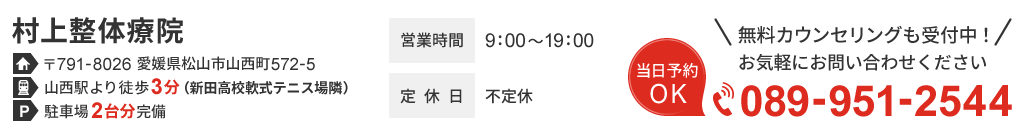八つのほこり
人間の体は、親神様からの「かりもの」で、心だけが自分のものであります。 身体をはじめ、身の周り一切は銘々の心通りにご守護くださいます。 親神様の思し召しに沿わない、自分中心の心遣いを「ほこり」と仰せられます。 ささいな「ほこり」の心遣いも積もり重なると、ついには十分なご守護を頂けなくなります。 そこで親神様の教えをほうきとして、たえず胸の掃除に努めるとともに、人には「ほこり」を積まさぬよう心を配らねばなりません。 ほこりの心遣いを掃除する手がかりとして「おしい・ほしい・にくい・かわい・うらみ・はらだち・よく・こうまん」という「八つほこり」をお教えいただいています。
おしいとは、心の働き、身の働きを惜しみ、税金など納めるべきものを出し惜しみ、嫌なことは人にさせて、自分は楽をしたいという心。 すべて、天理にかなわぬ出し惜しみ、骨惜しみの心遣いはほこりであります。
ほしいとは、心も尽くさず、身も働かずして、金銭を欲しがり、不相応に良き物を着たがり、食べたがり、また、あるが上にも欲しがるような心。 何事もたんのうの心を治めるのが肝心であります。
にくいとは、自分のためを思って言ってくれる人に、かえって気を悪くして反感を持ち、あるいは自分に気に入らない、癪に障る人を毛嫌いし、陰口を言って、そしり笑うような心。 また、銘々の身勝手から夫婦、親子など身内同士が、いがみ合うのもほこりであります。
かわいとは、わが身さえよければ、人はどうでも良いという心。 わが子を甘やかして食べ物、着る物の好き嫌いを言わし、仕込むべき事も仕込まず、間違ったことも意見せず、気ままにさせておくのは、よろしくありません。 また、わが身を思って、人を悪く言うのもほこり。 わが身わが子が可愛ければ、人のことも思い、人の子も可愛がらねばなりません。
うらみとは、顔をつぶされたとて人を恨み、望みを妨げられたとて人を恨み、誰がどう言ったとて人を恨み、根に持ち、銘々、知恵、力の足りない事や、徳のないことを思わず、人を恨むのはほこりであります。 人を恨む前に、わが身を顧みることが大切であります。
はらだちとは、腹が立つのは気ままからであります。心が澄まぬからであります。 人が悪いことを言ったとて腹を立て、誰がどうしたとて腹を立て、自分の主張を通し、相手に言い分に耳を貸そうとしないから、腹が立つのであります。 これからは腹を立てず、天の理を立てるようにするのがよろしいです。短期や癇癪は、自分の徳を落とすだけでなく、命を損なうことが有ります。
よくとは、人より多く身に付けたい、何が何でも取れるだけ取りたいという心。 人の目を盗んで数量をごまかし、人のものを取り込み、あるいは、無理な儲けを図り、暴利をむさぼる。 何によらず、値を出さずわがものにするのは強欲。また、色情に溺れるのは色欲であります。
こうまんとは、思い上がってうぬぼれ、威張り、富みや地位をかさに着て、人を見下し、踏みつけにするような心。 また、目上に媚び、弱いものをいじめ、あるいは頭を良いのに鼻をかけて、人を侮り、知ったかぶりし、人の欠点ばかり探す、これは高慢のほこりです。